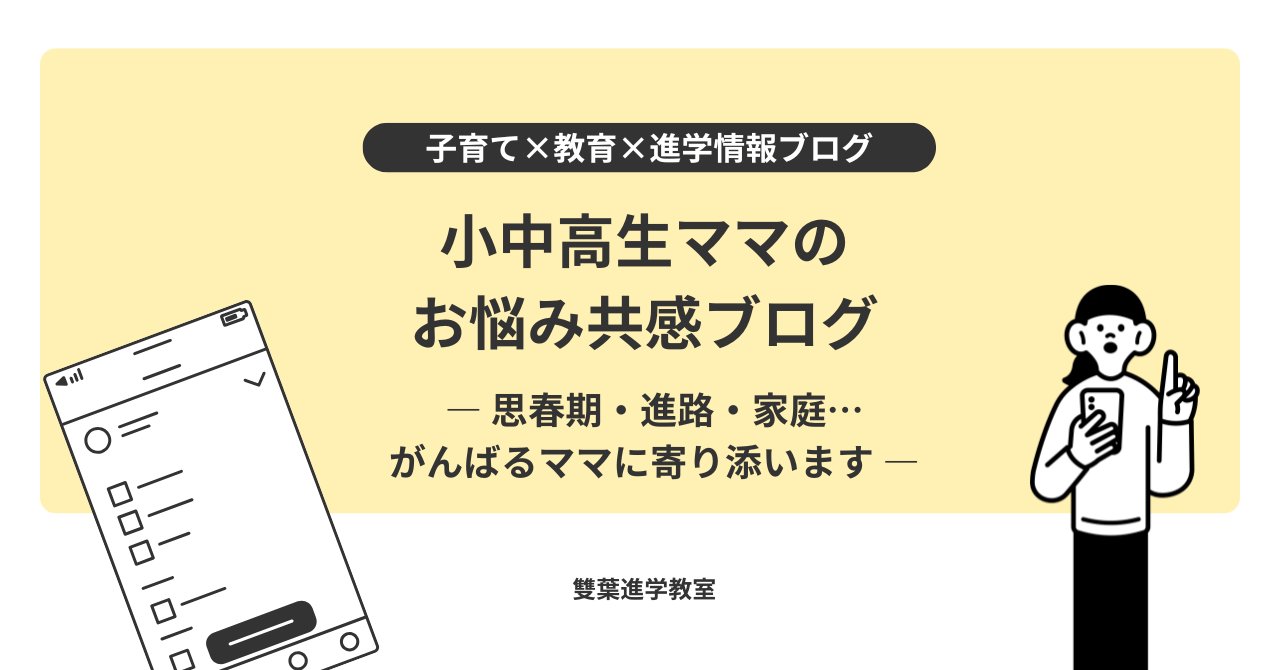Contents
その1 成績が下がってきて将来が不安
「最近、うちの子の成績がどんどん下がってきていて、このままで将来大丈夫なのか…」
そんな不安を抱えて、夜も眠れない日がある方へ。
大丈夫です。成績の低下には必ず理由があり、それを見つけて正しく対応すれば、挽回は十分可能です。
実際、これまで多くのご家庭が「あるポイント」に気づいたことで、子どもの学力を着実に取り戻しています。
そのポイントとは、「親の悩み方」ではなく「子どもへの関わり方」です。
この記事では、成績が下がり始めた時に親が陥りがちな思考パターンと、それをどう乗り越えるか。
さらに、現役塾講師の視点から見た「立て直しの具体策」もご紹介します。
将来への不安を、希望に変える第一歩として、ぜひ最後までお読みください。
1.「成績が下がってきて将来が不安」その理由
子どもが「成績が下がってきて将来が不安」と感じるとき、その背景にはまず「成績低下=未来の選択肢が狭くなるかもしれない」という親や子の思いがあるでしょう。実際、成績が落ちると学校・クラスでの立ち位置が変わり、「あの高校に行けないかもしれない」「将来の夢が遠のいたかも」と感じるケースも報告されています。
具体的には、次のような流れがあります:
- 定期テストの点数が少しずつ下がる
- 授業内容についていけず、自信を失う
- 「このままでは将来が…」という不安が生まれる
こうした流れを放置すると、子どもの“やる気”も低下しがちです。
そこで、成績低下を「将来が不安」という状態で終わらせず、まず原因を理解し、対策を始めることが解決の鍵になります。例えば、「どの教科・どの単元で点数が落ちたか」を親子で一緒に確認するだけで、安心・道筋が見えてきます。
このように、成績が下がってきて将来が不安という状態には明確なステップがあり、それを“見える化”して向き合えば、次の章以降で紹介するような有効な対応が可能です。
2.成績が下がる具体的な原因
なぜ「成績が下がってきて将来が不安」と感じる状況に陥るのか、その原因を把握することが非常に大切です。主な原因としては、以下の3つがよく挙げられています。
- 学習内容が難しくなった/スピードが速くなった:中学3年生になるとこれまでより応用が増え、基礎があいまいなままだと授業に追いつけなくなります。
- 勉強方法や習慣が合っていない:たとえば、教科書やノートを眺めるだけ、答えを丸写しするだけ、という方法では“理解”が深まりません。
- 生活リズム・学習環境が整っていない:夜更かし・スマホ・ゲームなどの影響で睡眠が不足すると、集中力・記憶力ともに落ちてしまいます。
具体例を挙げると、テスト直前「山のような問題集を一夜で…」と焦るあまり、基礎が抜けていて「公式の意味がわからない」「見たことのない問題が…」となる。このような状態だと“点数”も落ち、結果「将来が不安」という気持ちに直結します。
このように、成績が下がる背景には学習のギャップ・方法・生活習慣の3つが関係しており、まずはどこに“ズレ”があるかを確認することが、次の対策に向けての第一歩です。
3.「将来が不安」なままでにしないための緊急対策
「成績が下がってきて将来が不安」という状態をそのままにすると、さらに学習への意欲が落ち、悪循環に陥ることがあります。そこで、早めに立て直すための緊急対策をご紹介します。
具体的には以下のステップです:
- 小さな目標を立てて“成績が下がった状態”を止める
- 例:「次の定期テストで数学の90点→85点」など達成可能な目標を設定
- 復習・基礎固めをすぐに始める
- 基礎公式・用語を整理し、わからないまま先に進まないように
- 教科書・ノートを「眺める」だけでなく、「自分で説明できるか?」を確認
- 習慣化を支える親の役割
- 毎日固定の時間に机に向かう「習慣」をつける
- 子どもが「今日はやる気が出ない」と言ったとき、理由を聞いてあげる
- 子どもに合った勉強法を見つけるヒント
- インプット(読む・聞く)&アウトプット(書く・話す)をバランスよく取り入れる
こうした対策を実行すれば、「成績が下がってきて将来が不安」という気持ちが徐々に「今なら間に合う」という希望に変わっていきます。親子で早めに動くことで、悪循環を良循環に転じることが可能です。
- インプット(読む・聞く)&アウトプット(書く・話す)をバランスよく取り入れる
4.将来の選択肢を広げるために今できること
成績の話になると「受験」や「進学」など結果に目がいきがちですが、実は今できることをコツコツ積むことが将来の選択肢を広げる鍵です。
以下、具体策とその意義を挙げます:
- 成績だけが未来を決めるわけではないという視点
- 例:得意な教科が伸び悩んでも、好きなこと・興味があることを広げることも大切
- 成績改善+自己肯定感を育てる具体策
- 毎日の「できたこと」を振り返り、「今日の〇〇ができたね」と声かけする
- 小さな成功体験の積み重ねが「将来も頑張れる」という自信につながります
- 進路・高校選びのポイントを親子で話す
- 「何が好きか」「どんな生活をしたいか」を一緒に考える
- 選択肢として「普通科」「専門学科」など違う道があることを知る
- 塾・家庭学習・相談できる体制を整える
- 学校・家庭・塾が連携して子どもを支える環境を作ると安心です
これらを今着実に進めることで、「成績が下がってきて将来が不安」という心配が、将来を自分で選べる状態へと変わります。収拾がつかないと思われるときも、一つずつ「今できること」を実行していきましょう。
- 学校・家庭・塾が連携して子どもを支える環境を作ると安心です
5.親がやってはいけない5つの対応
時として、親の対応が子どものやる気をそいでしまい、逆に「成績が下がってきて将来が不安」という気持ちを加速させてしまうことがあります。以下は、避けたい対応とその理由です:
- 「怒る・責める」から始める
- 感情的な言葉が子どもにストレスとなり、学習意欲を下げる原因に。
- 「放置する」ことで深まる不安とズルズルの危険性
- 「どうしてるの?」の確認がないままだと、子どもは自分だけで悩み続けてしまいます。
- 子どもが“やる気を失う”言葉を使う
- 例:「なんで点数低いの?」→「どうすれば次良くなる?」の言い方に変える。
- 成績だけを見て評価を決める
- 成績=価値ではありません。努力・改善の過程も評価に入れましょう。
- 成績が下がったのは親の責任だと背負い込みすぎる
- 親もサポート役ですが、子どもが主体となる場面も必要です。
これらの“やってはいけない”対応を避け、代わりに「共に立て直すパートナー」として関わることで、子どもは安心して立ち直りに向けて動けます。むしろ親のサポート・安心感が「将来が不安」を希望に変える大きな力になります。
- 親もサポート役ですが、子どもが主体となる場面も必要です。
6.まとめ:成績の低下はチャンスでもある
「成績が下がってきて将来が不安」という状況は、確かに怖いものですが、改善のチャンスでもあります。なぜなら、次の理由からです:
- 今だからこそ「立て直し」が可能な理由:基礎部分に気づける時期だからこそ取り組みやすい。
- 小さな改善が将来の安心につながる:例えば毎日10分の復習が半年後に習慣となり、大きな成果を生み出します。
最後に、親子で「一歩を踏み出すためのチェックリスト」をご紹介します:- 定期テストの結果を一緒に振り返ったか?
- 毎日机に向かう時間を決めたか?
- 「今日できたこと」を振り返っているか?
- 子ども自身の目標(例:次のテストで〇〇点アップ)を立てたか?
これらを親子で一緒に進めていくことで、成績低下という“壁”を、将来を切り開く“ステップ”へと変えることができます。