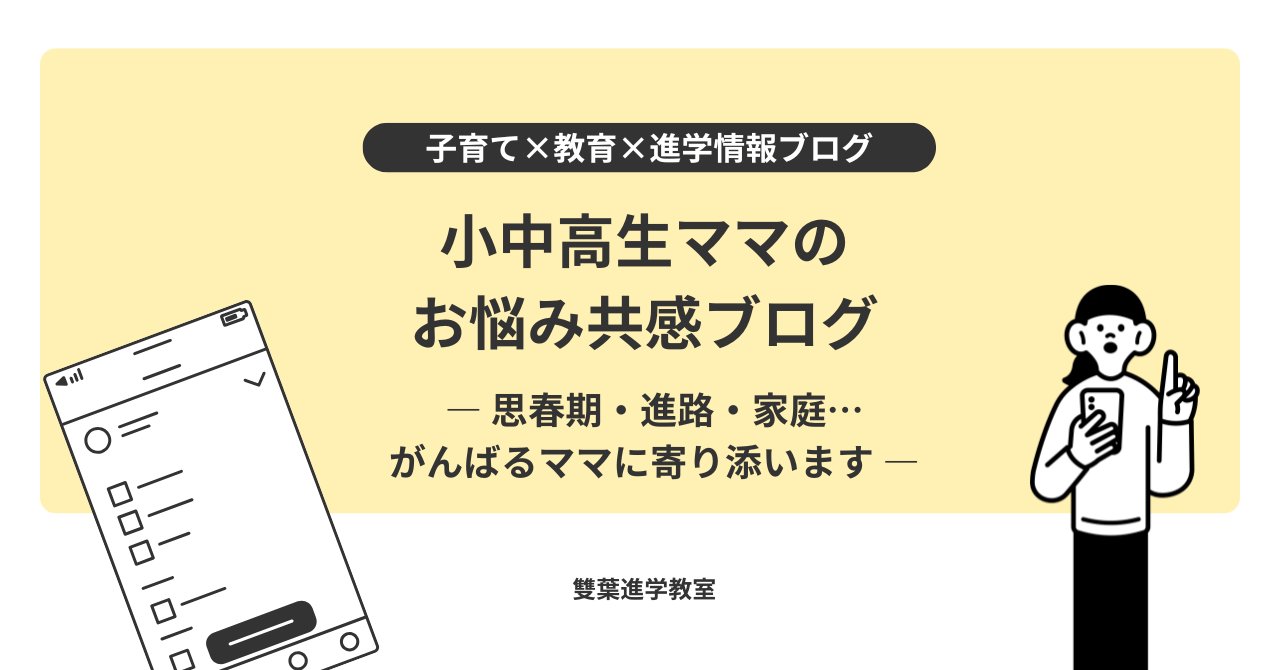「中学生になってから、急に勉強についていけなくなったみたいなんです……」
保護者の方から、こんなご相談を受けることがよくあります。
小学生の頃は普通にできていたのに、中学に入った途端、成績がガクンと落ちたり、「何をどう勉強すればいいかわからない」と言い出したり……。親としては「何が原因なの?」「自分にできることはあるの?」と戸惑ってしまいますよね。
でも安心してください。中学生の“勉強のつまずき”は決して珍しいことではなく、実はある「家庭でのサポートの仕方」で乗り越えられることが多いんです。
私は塾の現場で、そうした悩みを抱えたご家庭と何度も向き合ってきました。成績の下がり方やつまずき方には共通点があり、支援のステップを踏むことで、子どもたちは自信を取り戻していきます。
この記事では、中学入学後に「勉強がわからない」と感じ始めた子どもへの対応法を、保護者の方が家庭で実践できる形でわかりやすくお伝えします。
今すぐ始められるステップばかりですので、ぜひ最後までご覧ください。
Contents
1. なぜ「中学生になってから勉強がわからなくなる」のか?
中学生になってから急に「勉強がわからなくなった」と感じるお子さまは、実は少なくありません。それにははっきりとした理由があります。小学校から中学校へ進学することで、学習環境や内容が大きく変わるからです。
まず、授業のスピードが速くなります。小学校では、何度も同じ内容を繰り返して学ぶ機会が多くありましたが、中学校では「一度教わったら覚える」ことが前提になってきます。そのため、理解が追いつかないまま次の単元に進んでしまうお子さまが出てきます。
また、教科数が増えることも負担になります。英語や理科、社会など、小学校ではなかった本格的な学習がスタートし、内容の抽象度が一気に上がるのです。とくに英語は初めて学ぶルールが多く、苦手意識を持ちやすい教科です。
さらに、以下のような生活環境の変化も影響します。
- 部活動の開始による体力・時間の消耗
- スマートフォンやゲームなどの誘惑が増える
- 友人関係の変化によるストレス
このように、中学進学による変化は「学力面」だけでなく「生活全体」にも及びます。家庭での見守りと支えが、ますます大切になってくる時期です。
2. お子さまが“勉強がわからない”と感じ始めるサイン
「勉強がわからない」とお子さまが口にする前に、実はいくつかの“サイン”が現れることが多いです。保護者の方がその兆しに気づいてあげることで、早めの対応が可能になります。
まず注目してほしいのは、宿題の様子です。以前より宿題に取りかかるのが遅くなったり、提出しないことが増えたりしたら要注意です。「やりたくない」という気持ちの裏には、「やってもわからないから無駄だ」と感じている可能性があります。
次に、テストの点数や提出物の変化です。点数が下がった、授業ノートに空欄が目立つ、学校からの連絡で「提出物の未提出」があった場合は、理解が追いついていない兆候といえるでしょう。
また、以下のような発言や行動にも注意が必要です。
- 「何をどう勉強したらいいのかわからない」
- 「どうせやっても無理」といったあきらめの言葉
- 問題集や教科書を開かずに机の前でぼーっとする
このような様子が見られたら、「わからない」という気持ちがストレスになり、学習への意欲を奪っているかもしれません。まずは責めることなく、話をよく聞いてあげることが大切です。
保護者が子どもの気持ちに寄り添いながら、小さな変化に気づけるかどうかが、早期の学力回復のカギとなります。
3. 保護者が家庭でまずすべき支援ステップ
中学生になってから「勉強がわからなくなった」と感じているお子さまには、家庭での支援がとても大きな力になります。保護者ができることは限られているように思われがちですが、実際には家庭の対応一つで子どもの学び方が変わることも珍しくありません。
では、どのようなステップを踏めばよいのでしょうか? 以下の5つの段階で支援を進めていくのが効果的です。
ステップ1:どこでつまずいているかをチェックする
まず最初にするべきことは、「何がわからなくなっているのか」具体的に把握することです。
以下のような方法が効果的です。
- 最近のテストやワークを一緒に見てみる
- 「この問題はどこまでわかった?」と聞く
- 苦手な教科・単元を本人に書き出してもらう
「全部わからない」と感じているお子さまも、実は“ある単元”だけが苦手なことが多いです。原因を絞れば、対策も具体的になります。
ステップ2:まずは「復習・基本の理解」から戻る
理解が追いつかない原因は、前の学年や単元の土台が崩れていることにあります。そのため、教科書やワークを使って基本に立ち返ることが重要です。
たとえば数学なら、「正負の数」が理解できていなければ、「文字式」「方程式」もつまずきます。英語なら、「be動詞」と「一般動詞」の区別が曖昧なままでは、文章が書けません。
【具体例】
- 数学の問題集を1学年前から少しずつやり直す
- 英単語テストを毎日5語ずつ親子で確認する
- 理科・社会は小テスト形式で一問ずつ一緒に読む
“できた”を増やしてあげることが、次の学びにつながる第一歩です。
ステップ3:毎日の学習習慣を小さく始める(10分〜)
「勉強しなさい」と言われて、やる気になる子はあまりいません。そこで有効なのが、“短く・確実にできる”学習時間の設定です。
- 初日は「英語の単語10個チェック」だけ
- 習慣になったら「10分+計算プリント1枚」にする
- タイマーを使って「時間を区切る」のもおすすめ
大切なのは、“できた”という成功体験を毎日積ませることです。それが「自分でも勉強できるかも」という気持ちを育てます。
ステップ4:子ども自身に決めさせる「学習のルール作り」
勉強の時間や方法をすべて大人が決めると、子どもは「やらされている」と感じてしまいます。そうではなく、自分でルールを作ることで“主体的な学習”につながるのです。
【例】
- 「宿題をやる時間を自分で決めてカレンダーに書く」
- 「自分専用の“できたシール”を貼る表を作る」
- 「親子で週に1回『学習ふりかえり会』をする」
学習を自分のこととして捉えられるようになると、勉強への向き合い方が変わっていきます。
ステップ5:環境を整える(スマホ・ゲーム時間・勉強場所)
どれだけ頑張っても、集中できない環境では成果が出ません。中学生になってから勉強がわからなくなったと感じている子ほど、家庭の学習環境が見直しポイントになることがあります。
- スマホは「時間を決めて使う」ルールに
- テレビがついていない場所で学習させる
- リビングでの勉強も「気軽に質問しやすい」と好評
無理に取り上げたりせず、「いつ使って、いつ学ぶか」を親子で話し合って決めることが重要です。
このように、家庭でできる支援には「技術」ではなく「工夫」が必要です。一度にすべてやろうとせず、一歩ずつ、できるところから始めてみてください。
4. 教科別・つまずきやすい単元と家庭でできる具体支援
中学生になってから「勉強がわからなくなった」と感じるお子さまの多くは、特定の教科や単元でつまずいています。そのままにしておくと他の内容にも影響が出るため、早めに気づいて家庭でフォローすることが大切です。
ここでは、特につまずきやすい教科とその単元、そして保護者が家庭でできる支援方法をご紹介します。
数学:計算ミス・基礎の抜け・文章題の壁
中学生の数学で最も多いつまずきは、計算の基礎があいまいなまま進んでしまうことです。特に「正負の数」「文字式」「方程式」は、理解できていないとその後の単元すべてに影響します。
【よくある例】
- 符号のミス(−5+3など)
- 文字式のルールを覚えていない
- 式を立てる文章題で混乱する
【家庭でできる支援】
- 基本の計算プリントを1日5問だけ解く
- ミスした問題だけノートにまとめて「間違いノート」を作る
- 文章題は「登場人物・条件・質問内容」を一緒に図にして考える
「わかる」と「できる」は別なので、解説を読むだけでなく“手を動かす”時間を作ることが効果的です。
英語:単語・文法・授業に追いつけないパターン
英語は小学校で少し触れていたとはいえ、中学から本格的な学習が始まるためつまずきやすい教科です。
【よくあるつまずきポイント】
- 単語の意味・スペルを覚えられない
- be動詞と一般動詞の使い分けがわからない
- 疑問文や否定文を組み立てられない
【家庭でできる支援】
- 1日5単語ずつ「意味+読み+スペル」でチェック(音読も効果大)
- 「これはbe動詞?」「一般動詞?」とクイズ形式で質問
- 自分のことを英語で話す「今日の一言」を日課にする
英語は“慣れ”がものをいう科目です。まずは音読や暗記を楽しく繰り返す工夫が有効です。
理科・社会:暗記だけでなく“なぜ”を理解させる方法
理科や社会は、単に暗記すればよいと思われがちですが、“理解”がないとすぐに忘れてしまいます。
【よくあるつまずきポイント】
- 理科:実験の仕組み・計算問題の意味がわからない
- 社会:年号・地名・人物が頭に入らない
- 用語は覚えても、説明できない
【家庭でできる支援】
- 理科は図やイラストを一緒に見て「どうしてこうなるの?」を話し合う
- 社会は時代や地理を「物語」や「体験」に結びつけて話す(旅行、ニュースなど)
- クイズ形式で「○○って何だったっけ?」と声かけをする
暗記の前に“イメージ”や“ストーリー”で理解させると、記憶の定着が格段に良くなります。
家庭学習で使えるツール・ワーク・アプリ紹介
お子さまがつまずいている単元に合わせて、家庭で無理なく使える教材やツールを活用すると、支援がしやすくなります。
【おすすめツール】
- 学校で使っているワークを1〜2ページずつ反復練習
- 無料で使える学習プリントサイト(例:ちびむすドリル、学習プリント.com)
- スマホで確認できる暗記アプリ(使い方を家庭で決めておくのがポイント)
重要なのは「量」ではなく「習慣」です。毎日少しずつ、無理なく続ける仕組みを作ることが成功のカギとなります。
5. 保護者がやってはいけないNG対応と代替すべき言葉かけ
中学生になってから「勉強がわからなくなった」と感じているお子さまに対し、つい感情的になってしまう保護者の方は少なくありません。しかし、間違った関わり方をしてしまうと、お子さまのやる気をさらに奪ってしまう可能性があります。
ここでは、ありがちなNG対応と、その代わりに使ってほしい「前向きな言葉かけ」を紹介します。
よくあるNG対応①:「どうしてこんな問題もわからないの?」
この言葉は、本人にとって非常に強いプレッシャーになります。「自分はダメだ」と思い込んでしまい、やる気を失うきっかけになります。
【代替すべき言葉かけ】
- 「どこでつまずいたか一緒に見てみよう」
- 「この問題はちょっとややこしいよね。わからなくても大丈夫」
理解しようとする姿勢をほめることで、前向きな気持ちにつながります。
よくあるNG対応②:「○○ちゃんはできてるのに、なんであなたは…?」
比較は、子どもの自信を失わせる最大の原因の一つです。とくにきょうだいや同級生との比較は、親子関係にも悪影響を与えかねません。
【代替すべき言葉かけ】
- 「あなたができるようになったところを教えて」
- 「昨日よりできることが増えたね!」
「他人」と比べるのではなく、「過去の自分」と比べる声かけが効果的です。
よくあるNG対応③:「勉強しなさい!」「今すぐ机に向かいなさい!」
頭ごなしに命令されると、子どもは反発します。特に中学生は自立心が育ち始める時期なので、「自分で決めたい」という思いが強くなっています。
【代替すべき言葉かけ】
- 「今、何時から勉強始める予定だった?」
- 「○時から一緒に机に向かおうか」
自主性を尊重しながら促す言い方にすることで、反発ではなく行動につながりやすくなります。
よくあるNG対応④:つい先回りして答えを教えてしまう
「わからないならこうすればいい」とすぐに教えるのは、一見やさしいように見えて、考える力を奪う原因になります。
【代替すべき言葉かけ】
- 「この問題、どう考えた? 考え方を教えて」
- 「もう少しだけヒントを出すね」
子どもが“自分で解けた”という成功体験を積むことが、学習意欲の回復につながります。
親の声かけが子どもを前向きに変える
中学生になってから勉強がわからなくなるお子さまには、「安心できる家庭の雰囲気」が一番の支えになります。
言葉ひとつで、子どもの心は「やる気」にも「あきらめ」にも傾きます。
【前向きな声かけの例】
- 「少しずつでも、ちゃんと前に進んでるよ」
- 「今日のがんばり、ちゃんと見てたよ」
- 「あなたの成長が楽しみだよ」
叱るのではなく、信じて応援する姿勢が、子どもを勉強に向かわせる一番の力です。
6. 塾や外部サービスと協力するタイミングとポイント
中学生になってから「勉強がわからなくなった」と悩むお子さまを家庭で支えるのは大切ですが、すべてを家庭だけで抱え込もうとすると、親子ともに疲れてしまうことがあります。そんなときに活用したいのが、塾や外部の教育サービスです。
ただし、「いつ」「どんな塾を」「どう利用するか」が非常に重要です。やみくもに通わせるだけでは、かえって逆効果になることもあるため、慎重に判断しましょう。
外部支援を考えるべきサインとは?
以下のような様子が続いている場合、家庭での対応だけでは限界が近いと考えてよいでしょう。
- 家でどれだけ工夫しても、成績が改善しない
- 教科書の内容を見ても「さっぱりわからない」と言う
- 学校の授業が理解できず、置いていかれていると感じている
- 勉強そのものに強いストレスや不安を持っている
このような場合、早めに第三者の力を借りることで、状況が好転するケースが多くあります。
「塾選び」で見るべき3つのポイント
塾を選ぶときには、広告や評判だけで決めるのではなく、以下のような視点で見ることが大切です。
- 子どもと相性がよいか(教え方・先生の雰囲気)
→ 無料体験授業に参加し、子どもの反応を見る - 「わかる」から「できる」までフォローしてくれるか
→ 単なる問題演習だけでなく、苦手分析や復習指導があるか確認 - 家庭との連携がしやすいか(連絡や相談がスムーズ)
→ 定期的な面談や報告がある塾は安心感があります
子ども自身が「ここなら頑張れそう」と感じることが最も大切です。
保護者が塾に伝えるべき情報
塾に通わせる際は、お子さまの現状をできるだけ詳しく伝えることで、より的確なサポートが受けられます。
【伝えておくべきこと】
- 現在の成績や過去のテスト結果
- どの教科・単元で困っているか
- 家庭学習の様子(どんな反応か、どこで困っているか)
- 性格や集中できる時間帯など、学習に影響する特徴
“塾まかせ”ではなく、家庭と塾が一緒にお子さまを支える姿勢が大切です。
家庭でできる「外部支援との上手な付き合い方」
塾だけに頼るのではなく、家庭でもちょっとした工夫を続けることで、効果が何倍にも高まります。
- 塾で習ったことを家で「○○って習った?」と会話に出す
- 勉強内容を親に説明してもらう「教え返し」で定着を促す
- 塾のスケジュールを一緒に見ながら予定を管理する習慣をつける
家庭が「応援の場」であることを意識すると、子どもも安心して学びに向かえます。
7. まとめ:今すぐできる●つの行動と、長期的な視点
中学生になってから「勉強がわからなくなった」と悩むお子さまに対し、保護者ができる支援は、実はたくさんあります。ここまでお伝えした内容を踏まえつつ、ここでは「今すぐできる行動」と「将来を見据えた長期的な支援」の2つの視点からまとめます。
今日からできる5つの家庭サポート行動
- 1日10分だけ、一緒に教科書を読む時間をつくる
→ 「わからない」の原因を一緒に見つける第一歩になります。 - 最近のテストやノートを一緒に振り返る
→ どの単元でつまずいているかが明確になり、対策が立てやすくなります。 - 勉強に関する会話を“命令”ではなく“対話”に変える
→ 「宿題やった?」ではなく「今日はどこが難しかった?」と聞くようにします。 - スマホ・ゲームとの付き合い方を一緒にルール化する
→ 時間を奪う原因を“敵”にせず、“管理できるもの”に変える発想が大切です。 - 小さな成功体験を言葉でしっかりほめる
→ 「よくできたね」よりも、「この前よりスムーズにできたね」のような具体的なほめ方が効果的です。
これらはすべて、お金も特別な道具も必要なく、家庭ですぐ始められることばかりです。
中学生の「わからない」は、未来の「自信の芽」になる
長い目で見れば、「わからない」と悩むこと自体が、**“本気で学ぼうとしている証拠”**です。お子さまが困難にぶつかったとき、それを親子で一緒に乗り越えた経験は、将来の大きな財産になります。
長期的な支援のポイントは以下の3つです。
- 習慣を続けること:完璧を求めず、コツコツと
- 自立をうながすこと:「やらされる勉強」から「自分のための勉強」へ
- 失敗を受け入れること:失敗を「次の工夫」に変える柔軟さを持たせる
中学生の時期は、学力だけでなく“自分を信じる力”を育てる時期でもあります。
おわりに
この記事では、「中学生になってから勉強がわからなくなる」という悩みに対し、保護者が家庭でできる支援方法を教科別・段階別にご紹介してきました。
一人で悩まず、まずは今日から小さな一歩を踏み出してみてください。
保護者の関わり方ひとつで、お子さまは“学び直す力”を取り戻すことができます。